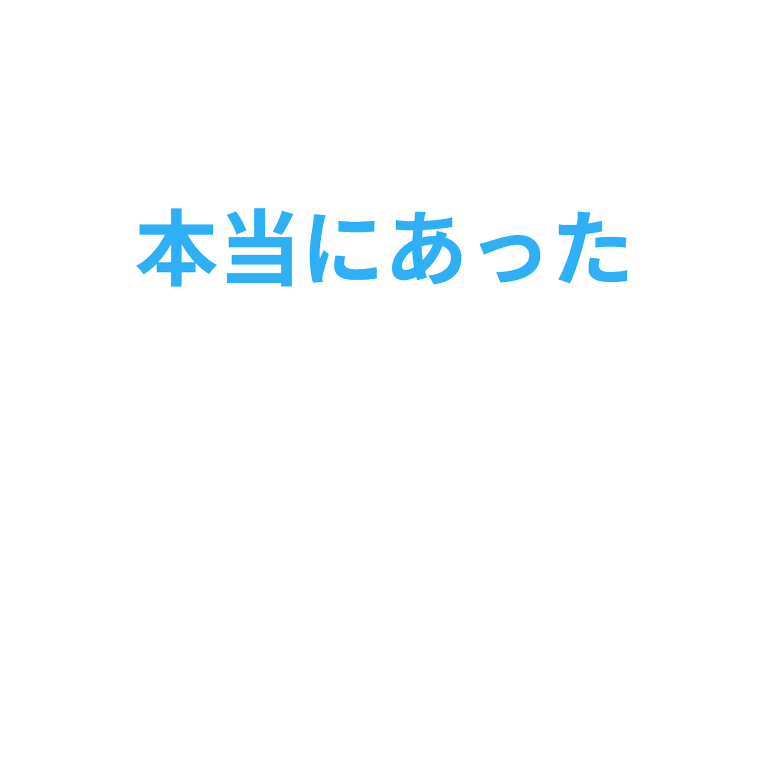
長編
迷い込んだ遭難者
しもやん 2日前
chat_bubble 0
38,381 views
メートルそこそこの低山連峰が南北に40キロメートルほど続く大規模な山脈で、関西圏のアクセスがよいのと三重県側の登山道が整備されているのもあり、行楽シーズンにもなれば登山者が引きも切らずに訪れる。標高が低いとはいえ、未整備の目立つ北部などは道が錯綜していたり、整備の進んでいる雨乞岳界隈でも下山方向をまちがえれば、それだけで深い谷の合流する擂鉢地獄のような迷い谷へ降りてしまうこともある。道迷いが深刻化して遭難するケースも多い。
われわれは提出されていた登山届をもとに、周辺の登山道をしらみつぶしにする計画を立てた。捜索班をふたつにわけ、登山届に記入してあったルートには多数の人員を配置し、辿ったかもしれない別ルートには少数を割り当てる。わたしは後者のグループだった。
主力部隊のA班は表道と呼ばれる尾根ルート、われわれ少人数のB班は裏道と呼ばれる沢ルート。分団長たちが近くの公民館でお茶をすすっているなか、若者たちはいっせいに入山した。
当日は外せない用事でこられなかった――これはサボりの婉曲的語法である――連中もいたため、われわれB班はたったの三人、おっかないお偉方や威張り散らした先輩もいない。消防団活動としては例外的な緩い雰囲気だったのを覚えている。
F岳はこの界隈に住んでいる人間であれば、数回くらいは必ず登っている地元憩いの場とも呼ぶべき山だ。標高は千メートルと少し、山頂まではだらだら休憩を入れても三時間以内で着く。頂上付近の広大なカレンフェルトの台地を目的に毎年相当数の登山者が訪れる人気山岳である。当然三人ともルートは知悉していた。迷い込みそうなポイントでは逐次立ち止まって声かけを行い、山腹や支沢に分け入って探してはみたものの、遭難者は見つかることなく避難小屋に着いてしまった。
避難小屋では先着していたA班の連中が弁当を広げて思い思いに雑談している。わたしたちもそれに加わり、情報を交換し合った。もちろん彼らも発見にはいたっておらず、当初の予定を変更して別ルートを使って下山したのではないかという意見も出ているとのことだった。
F岳は三重県側から以外にも、滋賀県側からのルートが(地図には記載されていないけれども)秘密裏につけられているし、山頂から南へは鈴鹿山脈を縦走できる稜線ルートもつけられている。登山者が登山届通りに行動しないのはよくあることだ。そうなると捜索範囲が広すぎて、とてもいまから計画を変更す
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。