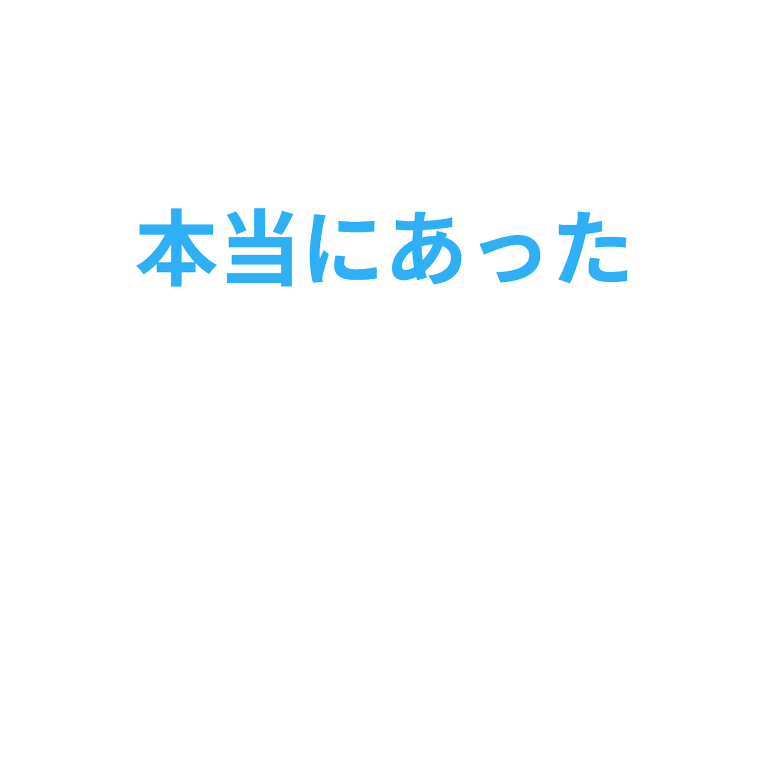
俺の地元は田舎だ。
夏になればヤマヒル、ムカデといった山特有の害虫がひっきりなしに家屋内に浸入して住民の安眠を脅かすし、冬は冬で洗濯物には高確率でカメムシがひっついている。1年中心の休まらない山奥の寒村。
ただ夏の川辺はすがすがしい風が渡る、かっこうの避暑地にはなる。いまでもシーズンになればリバーサイドがタープテントで埋め尽くされ、都市部からやってきた人びとの癒しの空間になる。川は流れが速いものの、川べりで水遊びをするぶんにはそれほどの危険もなく、子どもたちの歓声が実家にまで届いていたものだ。
その川の両端には歩行者が散歩できる程度の狭い堤防が作られていて、水害に備えられていた。地元の子どもたちは例外なく、堤防の坂を利用した草滑りをやったり、水遊びをしたり、ぞんぶんに田舎のメリットを享受していた。
これは俺が田舎に転校してきて2年ほど経った中学1年生のころ、夏休みの話である。
いつものように友人たちと堤防で遊んでいると、河村が妙なものを見つけた。彼は鬼の首を獲ったように騒ぎ立て、みんなのところへ息せき切って戻ってきた。話を聞いてみてもらちが明かない。〈すごいもの〉があるとばかりくり返すだけなのだ。
ぞろぞろと彼につきしたがっていくと、それはあった。堤防の側面に大きな穴がぽっかりと空いている。幅2メートル、高さは3メートル近くあるだろうか。馬蹄形のトンネルで、内部はコンクリートで舗装されているようだった。真夏の太陽が照りつける真昼間であるにもかかわらず、内部はほんの1メートルかそこらまでしか見通せず、どれくらい奥まで続いているのかはわからない。
みんなその穴を前にして呆然と立ち尽くしていた。いま考えてみれば増水時に水をよそへ逃がすための排水路だったのだろうが、当時の俺たちはこの穴がなぜ存在しているのかまったく想像できなかった。想像できないものには好奇心と、恐怖心がつきまとう。にわかに興奮が湧きおこり、潜入するのしないだのの大騒ぎが始まった。
すぐさま探検隊が選抜された。俺、発見者の河村、それにグループ内ではカーストの低い林の3人である。俺は男らしいところを見せたかったし、興味もあった。河村は言いだしっぺゆえの責任を感じているようだった。わからないのは林の動機だった。誰からも強制されたわけでもないのに、真っ先に志願したのである。数日前に催された肝試しで喉が枯れるほど悲鳴を上げていた林が。
後日談:
後日談はまだありません。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(5件)
コメントはまだありません。


