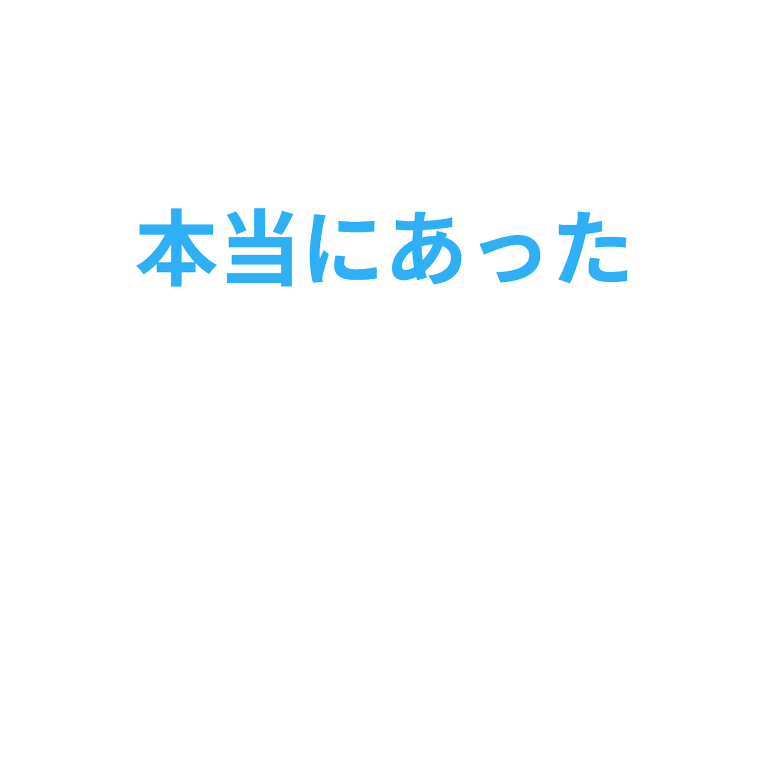
日が沈みきる数分前の空は、光の名残を惜しむように金と藍の層を織り交ぜていた。
その下で、三人の男たちが海に浮かんでいた。
AとBは波待ちをしながら談笑している。
「なんだかんだで、久しぶりだな」「そうだな、三人揃うのは二年ぶりか?」
――けれど、Cは笑っていなかった。
沖を、見ていた。
その目は何かを見ているようで、何も見ていない。
次の波が来る前に、Cはゆっくりとボードから足を下ろした。
そして、海から上がると、無言で砂浜を歩き始めた。
「……おい、C?」
Aが声をかけた。反応はなかった。
ボードも濡れたスーツもそのまま、Cはそのまま砂丘の向こう――森へと入っていった。
AとBはあわてて追いかけた。
その時点ではまだ、「変なことになった」とは思っていなかった。
Cが体調を崩したとか、何か急に思い出したとか、そんな類の事だと――
だが、森に入った瞬間、空気が変わった。
音が遠い。風もない。
木々の間を縫うような道はなく、ただ鬱蒼とした緑が口を開けていた。
そして、そこには**地図にないはずの“奥行き”**があった。
Cの姿は見えない。
足音も、影も、残っていない。
AとBは何も言わず、ただその場に立ち尽くしていた。
「……なあ、A……」
「ん」
「なんか、波の音、聞こえねぇか……?」
Aは一瞬、聞こえないと答えようとした。
だが、耳を澄ますと――確かにそれはあった。
この森の奥から、潮が満ちるような音が、波打ち際のように、ゆっくりと近づいてくるのだった。
AとBは小走りで引き返した。
森の奥には進まなかった。進めなかった。
戻る途中、振り返ったAは、視界の隅に白い影を見た気がした。
――風で揺れる布のようだった。
――それとも、人のようだった。
海に戻ると、空はすっかり夜だった。
Cの姿はなかった。
波の音だけが、深く、静かに、満ちていた。
警察の報告は、簡潔だった。
「30代男性・C氏が海岸から離れ、森に入ったまま戻らず。目撃者は二名。
遺留品はサーフボードとウェットスーツ一式。森に足跡なし。」
佐原敬一は、その報告書を読みながら無意識に額に触れていた。
現職の警察官ではない。彼は「補助員」だ。
県の文化財保護課と提携した、民俗信仰や土着伝承に関わる「調査対象」の一次判定要員。
人が“理屈ではない何か”に触れたとき――佐原の出番が来る。
彼はその日、単身で表浜の海岸へ向かった。
⸻
風はほとんどなく、砂は乾いていた。
日中でも人影はまばら。
後日談:
- 以前別の怪談サイトにも投稿した話です。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。


