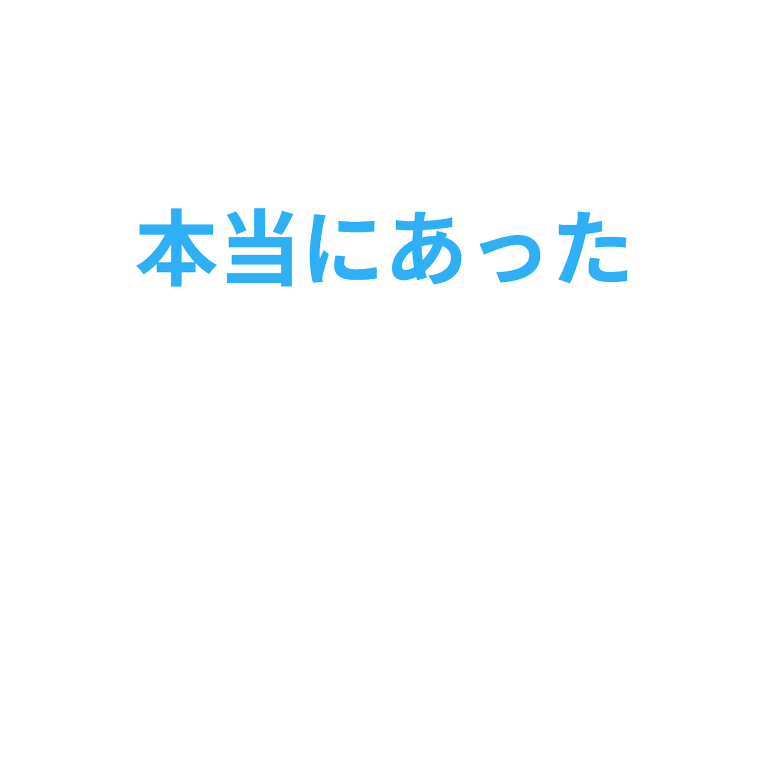
長編
緑の文化大革命
しもやん 3日前
chat_bubble 0
15,771 views
至高の価値を持つとかいうことにはならない。このシステムがうまくいっているのはまさにその特性そのもの――参加しているプレイヤーが自己の利益を最大化するからである。アダム・スミスが言っているように、個人が利己的にふるまえば市場の〈見えざる手〉が価格を通して消費者に情報を伝達し、おのずから秩序が生まれるのだ。
生物が自己の利益を最大化するよう進化してきたのなら、上述した資本主義の理論がそのまま当てはめられる。生態系は調和を保っているように見える。生産者-捕食者-分解者の構図は見事だし、植物が二酸化炭素を消費して酸素を放出するのは奇跡のようだ。しかしそうではない。
生産者(植物)が生まれたのは単に日光を利用するのがその時点でもっとも最適な戦略だったからだ。捕食者(動物)は植物を食べて手っ取り早く糖を補給するのが楽だったのだ。分解者(細菌類)にとってはそこらに転がっている死体から養分を得るのがもっともコストのかからないやりかただった。
こんにちわれわれは植物の放出する酸素を後生ありがたがって吸っているけれども、連中が進化する前は地球上に酸素を必要とする生物はいなかった。彼らは嫌気性生物と呼ばれ、酸素に触れれば即お陀仏となる。植物が酸素という毒を地球にまき散らし始めたころ、彼らは酸素の届かない場所に逃げるしかなかった。それは沼の底であったり人間の腸内であったりする。現在の環境は単に、酸素という毒を利用することに成功した子孫が繁栄している世界にすぎない。
* * *
以上の議論から、わたしは読者が〈自然主義の誤謬〉のなんたるかを理解したものと信じる。
自然は正しいどころかいき当たりばったりで乱脈経営をやらかす、三流以下の経営者であることがわかった。自然淘汰は未来予知などできない。神は進化にまったく関与していないのだ。そうであるならば、現代の自然に対する異常なまでの崇拝は常軌を逸しているとしかいいようがない。
もちろん自然には見習うべき点はある。だが人びとが目を背けたくなるような負の部分は厳然と存在する。鳥類はおしどり夫婦なんかではない。表向き一夫一妻を貫いているように見えるけれども、生まれてくる雛の30%ほどはべつのオスの子どもである。あらゆる種でレイプはさかんに行われている。自然が絶対的に正しいとのたまうならば、こうした負の側面にも向き合う必要がある。見えないふりをするのは
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。