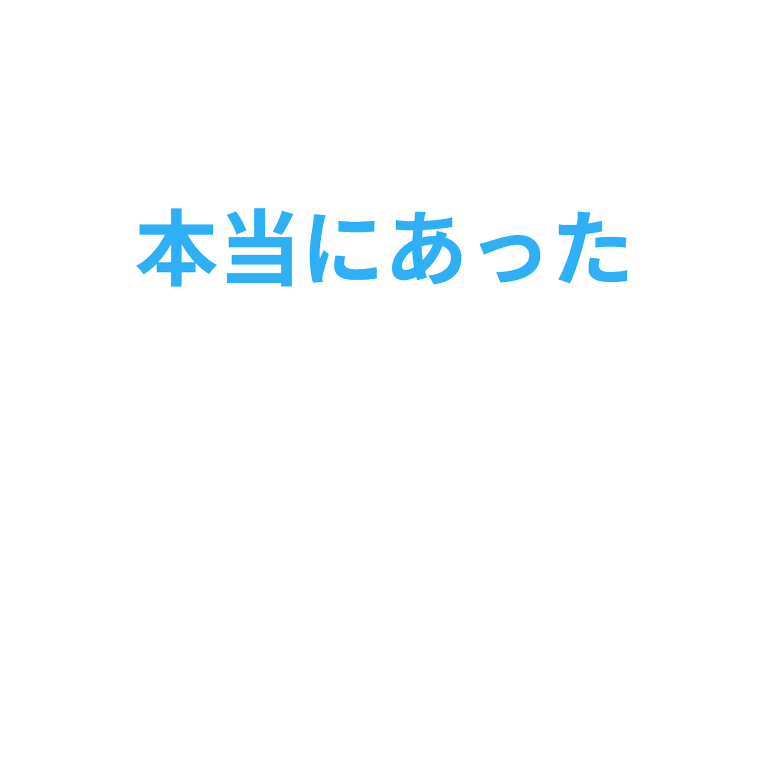
氷獄の都
寒秋の冷気が頬を撫でるのを感じながら、俺は人気の無いバス停でただ1人バスを待っていた。
目的地は駅。何かしらの用事があるわけではないが、なんとなく実家に帰りたくなったのだ。
帰ったらまず何をしよう。湯船に浸かってゆっくりしたい。
そんなありふれた思いを何の気なしに馳せながら、車通りが少ないが無駄に幅の広い道路の路肩に設置されたバス停のベンチでバスを待つ。
スマホで確認したこのバス停へのバスの到着予定時刻は16時30分。現在の時間は16時22分で、あと8分ほどもこの寒い中待たなければならない。吐く息が白く染まっているのを確認して、俺はスマホ片手にマフラーを口元まで持っていっては、沈み行く夕日を眺めた。
しばらくして、予定到着時刻より2分ほど早いにも関わらずバスが到着する。スマホの画面を見ていた俺は、乗客のまばらなバスを見て、予定より早く来て出発するのはいいことなのか?と多少の疑問を抱きながらも、口を開けた乗車口からバスの中へと入っては、前の方の席へと向かった。
俺以外このバス停から乗る乗客はいなかったので、俺が乗り込んだのを確認した運転手はすぐさま扉を閉めて発進する。
「次は氷獄の都、氷獄の都〜。お降りの方はボタンを押してお知らせ下さい」
俺が席に着くと同時に車内アナウンスが鳴り響いた。ここで俺は再び疑問を抱く。
俺はたまにだが駅行きのバスを使う。もちろん先程乗ったバス停から乗り込んで、だ。だが、駅へと向かう途中で『氷獄の都』なんていう名前のバス停は聞いたことがなかった。
そうして俺は乗る予定だったバスを間違えたことに気づき、バスに乗り込む際にスマホを見ていてこのバスの行先表示を見ていなかったことを後悔する。そしてすぐさまスマホで「氷獄の都」と検索した。とりあえず一番上に出てきた「氷獄の都・TOP」と書かれたページを開く。
まず目に飛び込んできたのは、『氷獄の都』とまるで血が飛び散ったかのようなフォントで描かれた、不気味な見出しとその背景として存在する微笑を浮かべたおかっぱ頭の日本人形だった。
いや、ホームページじゃなくてバスの時刻表を見ないとな。
後日談:
後日談はまだありません。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。


