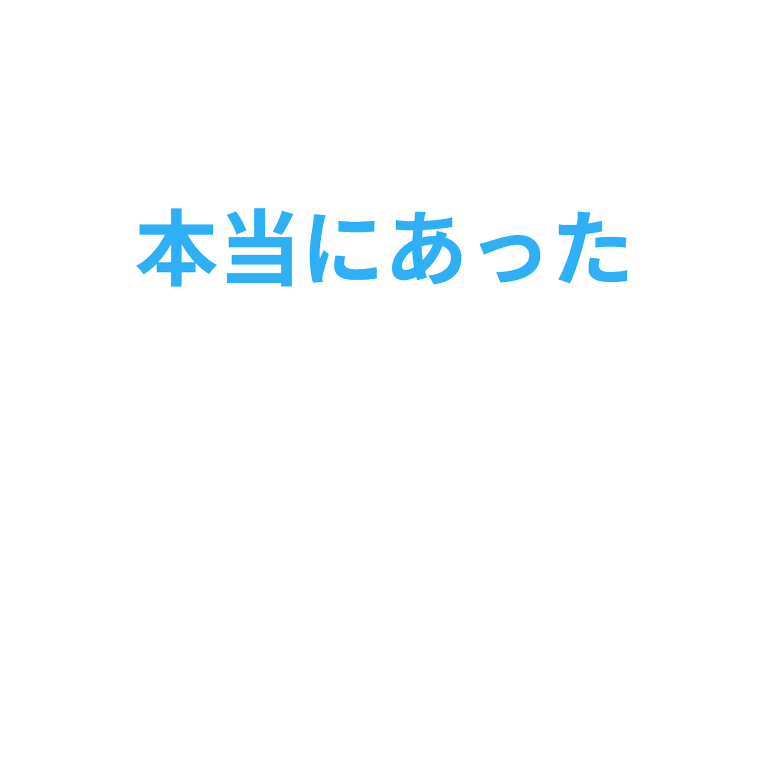
僕が小学生低学年の頃、大阪のとある団地に住んでいた。
10階建の5階 502号室だったと思う。
両親は共働きで夕方19:00頃まで帰って来ない。
よく居る鍵っ子ってやつだ。
僕の住んでいた団地にはそこそこ大きな公園があり公園を取り囲む様に別館が立ち並ぶ。
別館には同じ学区の年の頃が変わらない友達や少し年下の良く遊ぶ男の子達、不良っぽい年上とかもいて、毎日団地の公園で色々な人達と子供ルールで色々遊んで両親の帰りをその公園で待って時間を潰した。
ある日、ブランコ遊びをその団地の男友達として「靴飛ばし」「座り漕ぎでどっちが高く漕げるか?」子供がブランコで考えられる遊びを思いつく限りやっていた。
男友達の1人がブランコで立ち漕ぎを始めた。
凄い勢いでスイングするブランコ
「ほら見てみて凄いだろ!」
男友達は競う様に皆んなで立ち漕ぎをはじめて
そんな大人気のブランコ遊びだが男友達は自分を含め五人。
ブランコの席は4席
ブランコで遊べない余った男の子は、
僕の前にやってきて、
僕の立ち漕ぎブランコの前に向かい合う形で乗って来た。
「こっちの方が凄いぞ!」と他の男友達の視線を集める。
向かい合った男友達友達がブランコを漕ぐ
そしてその後僕がブランコを漕ぐ
リズミカルに2人でブランコを漕いでいると
その勢いは鎖を吊るす上部の鉄柱より高く上がり
ほぼ垂直に落ちる勢いでブランコはスイングする。
そんな勢いでスイングするブランコの遠心力を小学校に上がりたての僕が鎖を掴んで居られるわけもなく僕はスイングする遠心力をブランコの最上部で支える事が出来なくなり、
「ビタン!」と水泳の飛び込みの失敗した時の胸打ちあの感じを硬い地面で体感する事になった。
うつ伏せの状態で地面に打ち付けられた視界は公園の広い地面を地平線の様に眺める感じ、
何故だか痛みは感じなかった。
地面の茶色い砂
高さ1Mくらいのコンクリート塀の灰色
空の青
ブランコの太く曲がった鉄柵の黄色
それらが徐々に灰色の世界へと変わっていく。
僕は怖くなって声を出す!
「たすけて!」
たしかに発した言葉 。
ただこの灰色の世界では自分の声は自分に聞こえない。
たしかに「たすけて!」と自分が発している感覚はあるのだ。
喉の微弱な震えとかそういう感じはたしかに周りにははっきりと聞こえているいつもの感じその自覚はあるが自分の耳には音として入ってこない!
慌ててもう一度ど「たすけて!」ど叫んだ。
やはり自分の耳には声が聞こえない。
やばい!やばい!やばい!
「たすけて!」
後日談:
- 結構ガチ目にあった記憶。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。


