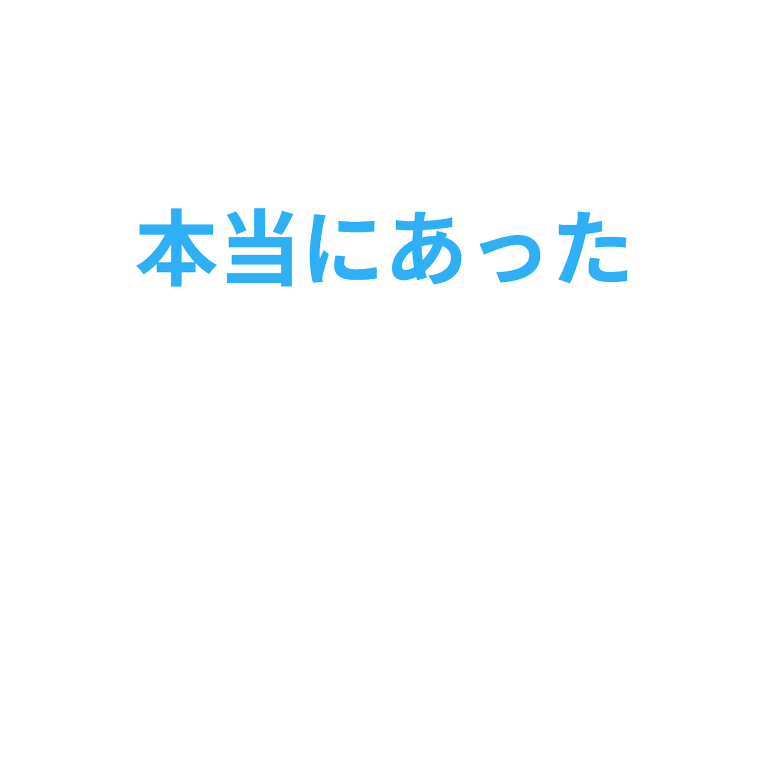
山では見知らぬ他人との距離が不思議と近くなる。
すれ違えばあいさつをするのは当たり前だし、フィーリングが合えば長々と山談義をしたりもする。
目的地さえ合えば、道連れになることさえそう珍しくはない。
以下に語る話はわたしが若いころに遭遇した、とある女性登山者との邂逅の記録である。
記憶が風化しつつあるいま、少しでも多くの人に知ってもらうため、不特定多数の読者が得られる場に投稿することにした(会話や情景描写は覚えている限り正確に書いたつもりだが、年月が経つあいだに脳の補完を受けている可能性があることをあらかじめ断っておく)。
もう10年以上も前の話になる。
* * *
20代前半のころのわたしは粗末なガイドブックを片手に、手ごろな山へなんの予習もなしに突撃をくり返す猪武者のようなスタイルだった。
無知とは恐ろしいものだ。出版年の古いガイドブックに記載されたルートは廃道と化していることもままあり、現場で往生した経験も一度や二度ではない。
それでも若さゆえの勢いでいろんな低山へ突っ込んで蜘蛛の巣だらけ、ヒルまみれになって命からがら帰ってくる。そんな無謀な山行が実に刺激的であった。
記憶があいまいなのだが、あれは秋も深まってきた鈴鹿山脈での出来事だったと思う。
例によってガイドブックに記載されていた藤原岳へ、なんの予習もなしに裏道(聖宝寺ルート)から登り始めた。
聖宝寺ルートは表道(大貝戸ルート)ほどではないが、十分整備された一般道である。1合めごとに指導標が建てられ、木々には等間隔でペナントが巻いてある。いまのわたしなら目をつむっていても登れるようなルートだ。
とはいえ沢から尾根に道が切り替わったり、山腹をジグザグに登ったり変化に富んでいるため、現在位置をロストしやすい面は否めない。当時の〈山感覚〉が備わっていなかったわたしは案の定、道に迷った。
経験の浅かったわたしはパニックを発症してしまった。道の通されていない藪がちな尾根をあてもなく彷徨い歩き、大声で助けを求めた。死の恐怖に憑りつかれていた。
単独登山での道迷いほど心細いものはない。晩秋の山は生命の息吹が感じられず、木枯らしが吹くたびに葉の落ちた木々がざわめく。そのさまはなんとも言えず不気味だった。
万策尽きて怒鳴る元気もなくなり、切り株に腰かけて頭を抱えていると、人の呼ぶ声が聞こえてくることに気づいた。近い。
「ねえ、誰かいるの」
後日談:
後日談はまだありません。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。


