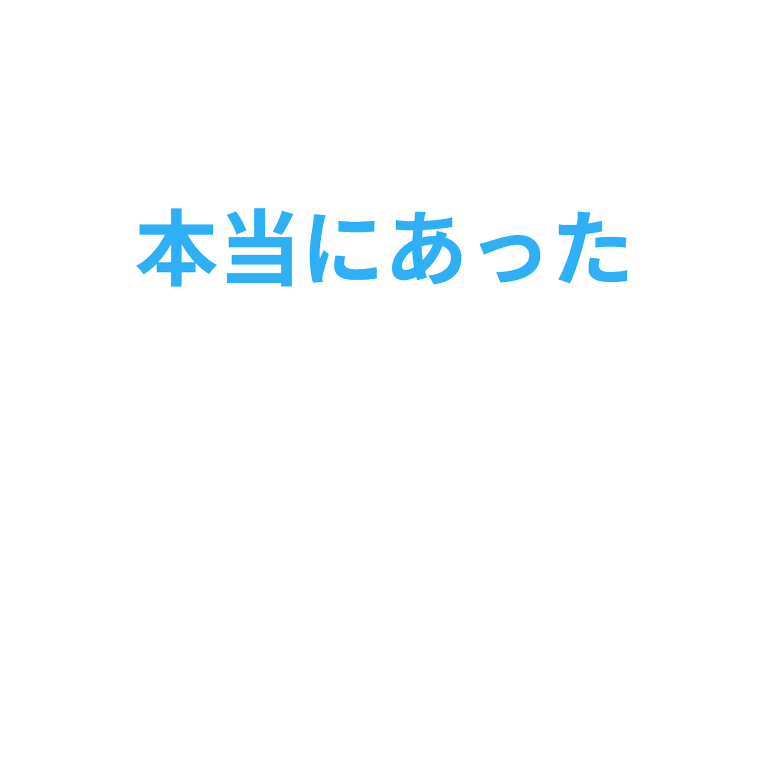
日本アルプスのうちでどこが好きかと聞かれれば、わたしは迷わず中央アルプスだと答えるだろう。
荒々しい岩稜と多数の名峰を擁する北アルプスでも、手つかずの自然が残っている南アルプスでもない。山脈の規模が小さい、3,000メートル峰がない、ロープウェイで庶民化されたなどと散々な言われようの中央アルプスが、なぜか好きなのだ。自宅からもっともアクセスがよいというのもあるのだろうが、山脈自体がコンパクトにまとまっており、日帰りでもアプローチしやすい点は長期休暇の取りづらいサラリーマンにとって、心強い味方である。
どの山域にもフリークはいるものだ。そのエリアを知り尽くし、一般登山道はもちろんのこと、バリエーションも数多くこなす一種のマニア。この手の山屋は愛着を持った山域に入り浸っているので、そこへ行けば高確率で顔を合わせることになる。
若いころは横溢する体力を持て余し、夏季ともなれば毎週のように中央アルプスへ出かけていったものだ。
そこでわたしは、一人の中央アルプスフリークと出会うことになる。
* * *
わたしは30歳前後の全盛期のころ、中央アルプス南部をよく攻めていた。檜尾岳、空木岳、南駒ヶ岳、仙涯嶺、越百山。ロープウェイの架設された北部の賑わいから隔絶され、森閑と静まり返った南部は、人混み嫌いのわたしにとって居心地のよいフィールドであった。
その日は確か9月の下旬で、カラリと晴れ渡った絶好の登山日和だったと思う。木曽谷から南駒ヶ岳へ至り、さらに北上して赤梛岳~空木岳をハント、駒峰ヒュッテで一泊後、木曽殿越えから木曽谷へ下山するというコース取りだった。
9:00ごろ木曽谷の駐車場を出発し、終始急登の南駒ヶ岳への登りを無心になってこなす。直下のハイマツ漕ぎで体力を根こそぎ持っていかれ、南駒ヶ岳(2,841メートル)に這い上がった時点で14:30になっていた。ザックを下ろして心地よい風に吹かれていると、南側の越百山方面から単独の男性が登ってきた。
短く刈ったごま塩頭に迷彩柄のバンダナを巻き、東条英機のような縁なしの眼鏡をかけた初老の男性。わたしはこの人物と会うのがこれで4回目だった。それもすべて中央アルプスである。特徴的な見た目なのでいやでも覚えてしまい、2回目以降はそれとなく意識するようになっていた。眼鏡の形から、わたしは彼のことを心中で〈東条さん〉と呼んでいた。
後日談:
後日談はまだありません。
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(1件)
コメントはまだありません。

