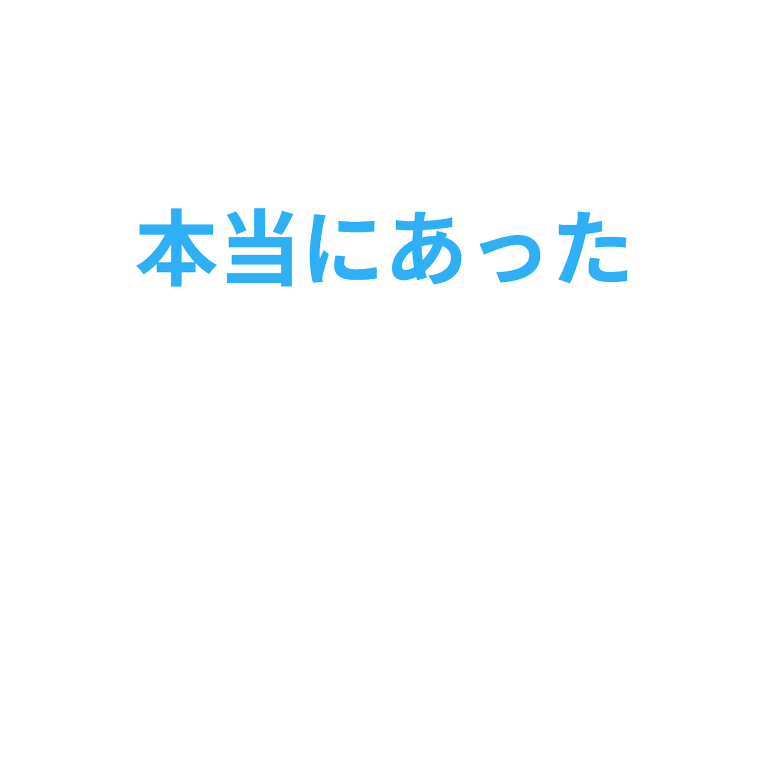
長編
たゆたう山々
しもやん 3日前
chat_bubble 0
16,707 views
その観測行為自体が擾乱要因になって、電子になにがしかの影響を与えてしまう。電子はエネルギー的に励起されて自然の状態ではなくなる。電子の位置を特定すれば運動方向がぼやけるし、運動方向を特定しようとすれば位置がぼやける。〈ハイゼンベルクの不確定性〉だ。
もし電子の位置をX、Y、Zの3座標で表現できないなら、どうなるのだろうか。量子力学では電子の位置を確率の波として記述する。位置を確定できないのだから、電子は部屋いっぱいに広がっていて、観測した瞬間に1点へと収斂するというのだ。これは〈波動関数の収束〉と呼ばれている。
電子が空間に広がっているようなあいまいな存在なら、究極的には俺たちの住むマクロ世界もそうなっていない保証はどこにもない。なんといってもすべての物体は陽子と電子でできているのだから。マクロとミクロの境界はすこぶるあいまいである。電子がミクロで野球ボールはマクロ。異論はないかもしれないが、ではウイルスはどうか。むき出しのDNAは十分に小さい。いったい誰が量子力学的な効果の出始める境界を決めるのだろうか。
久しぶりに通る道を歩いていて、ふと違和感を覚える瞬間は誰にでもあるはずだ。いつの間にあんなでっかいビルが建ったんだろうとか、いつか入ってみようと思っていたカフェがどうしても見つからないとか。自宅に帰ってきて服を脱ぎ散らかし、コーヒー片手に一息入れた瞬間、家具の位置が微妙に変わっているのに気づく。
コペンハーゲン解釈は観測によって波動関数が収束すると主張する。電子だけではなくこの世界そのものでさえも量子的な重ね合わせ状態になっており、観測されるまではさまざまな姿がダブっているというのだ。箱に入った猫は死んでいると同時に生きてもいる。中峠の入り口を示す道標は観測されるまで存在していないかもしれない。ブナ清水と呼ばれる湧水は、ハイカーにも見つけられるほど明確な位置にあることもあれば、登山道から大きくはずれた斜面にひっそりと湧き出ているのかもしれない。それは誰かが観測するまでわからない。そして観測者がいなくなれば、再びあいまいな確率波として空間に発散する。
晩秋になってヤマヒルも鳴りを潜め、落ち葉の堆積する肌寒い鈴鹿を歩いているとき、俺は例のごとくルートミスをやらかす。何度も歩いている通勤路のような登山道のはずなのにと首を傾げながら戻る。そんなとき俺は何重にもたゆたって登山者を幻惑する、量子力学
この怖い話はどうでしたか?
chat_bubble コメント(0件)
コメントはまだありません。